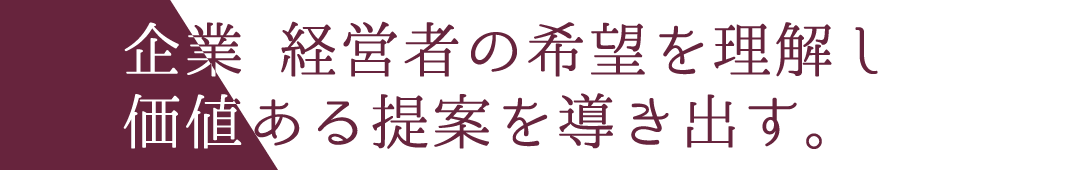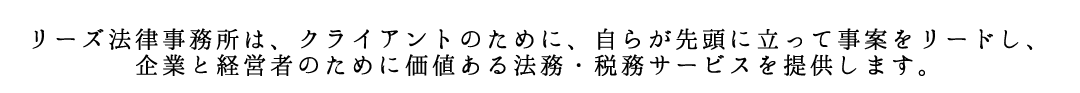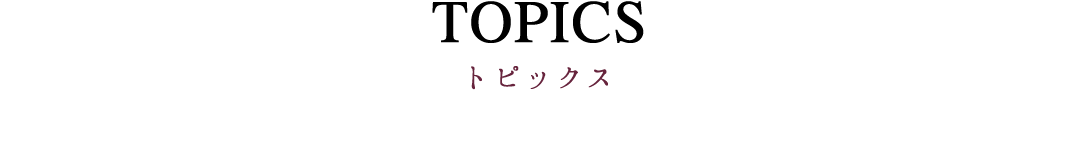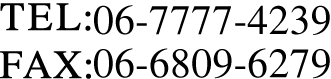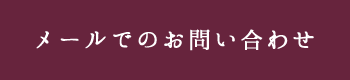-
2024.02.10 ブログ 裁決事例の公表(消費税関連の一事例)
-
2024.02.06 ブログ 【利用規約】ECサイトの利用規約の作成上の留意点
-
2023.10.24 ブログ 査察事件の流れ
-
2023.06.13 ブログ 【役員報酬】不相当に高額な場合の損金不算入について
-
2023.04.13 ブログ 【景品表示法】過大な景品類の提供の禁止
-
2023.02.23 ブログ 【特定商取引法】通信販売のクーリング・オフについて
-
2022.12.31 ブログ 【労働法】有期労働契約~雇止めと無期転換~
-
2022.08.03 ブログ 【国際税務】タックスヘイブン対策税制について
-
2022.05.29 ブログ 【Business Management Visa】経営管理ビザと法令遵守
-
2022.05.14 ブログ 【相続税・財産評価通達6項】最高裁令和4年4月19日判決
-
2022.04.06 ブログ 【景品表示法】違反した場合どうなるか?どうするか?(2)
-
2022.02.10 ブログ 【景品表示法】違反した場合どうなるか?どうするか?(1)
-
2022.01.31 ブログ 【税務】税法における「居住者」・「住所」の問題
-
2022.01.08 ブログ 【税務調査】暗号資産で得た所得に対する課税
-
2021.11.16 ブログ 【相続税】経営者の「貸付金」を相続財産としないためには?
-
2021.11.16 ブログ 【税務】飲食業や建設業など現金商売ならではの問題
-
2021.09.01 新着情報 【書籍刊行】企業法務で知っておくべき税務上の問題点100
-
2021.08.22 ブログ 【法人税】同族会社の行為計算否認と第三者割当増資
-
2021.05.24 ブログ 【ベンチャー投資】J-KISSなどコンバーティブル・エクイティの法務と税務
-
2021.03.28 ブログ 【役員報酬の税務】D&O保険料を会社が払う場合