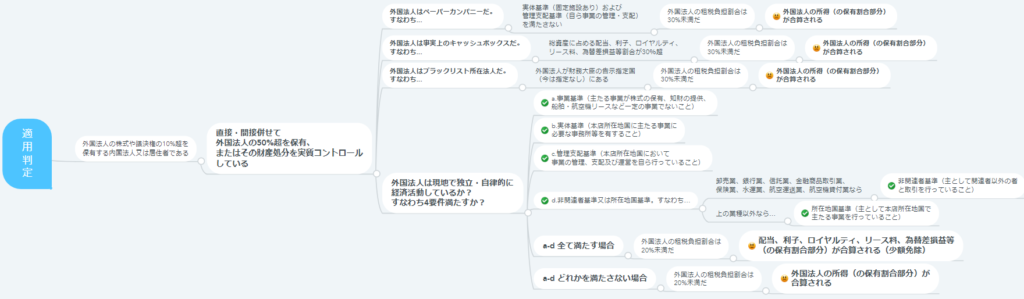【労働法】有期労働契約~雇止めと無期転換~
はじめに
今日、企業において、いわゆる正社員(期限の定めのない労働契約を締結している労働者)ではなく、有期労働契約を締結している労働者が数多く存在していることは皆様もご存じだと思います。
さて、このような有期労働契約を締結している労働者について、労働法がどのような保護を図っているか、皆様はご存じでしょうか。
以下では、主に、有期労働契約をしている企業に向けて、一般的な留意点を解説したいと思います。
「雇止め」とは
まずは、いわゆる「雇止め」です
雇止めは以下のように定義されています。
雇止め:期間を定めた労働契約の期間満了に際し、使用者が契約の更新を拒絶すること
良く知られているように、有期労働契約期間が5年を超えると、無期転換権(期間の労働契約に転換することができる権利)が発生し、これにより、当該労働者は、期間定めのない労働契約を会社に対して申し込むことができます。
この有期労働契約期間の5年目に際して、雇止めの問題が生じるのです。
すなわち、無期転換権を定めたのは、有期労働者の雇用の安定を図るためであり、発生要件である労働期間が「5年」の直前でなされた雇止めは、脱法行為である疑いがあるとして、雇止めをしなければならない必要性が相当に強固な場合を除き、雇止めが無効とされる場合が相対的に高くなります。
企業としては、労働契約法18条、19条により雇い止め法理が制定法化され、労働者の保護がより強化されたことに留意する必要があります。
では、2年間や3年間勤務した場合の労働者に雇止めをすることについては、問題ないのでしょうか。
結論としては、2、3年後の雇止めでも、必ずしも労働契約法19条に抵触しないわけではありません。過去の判例でも、5年に満たない場合であっても雇止めを無効とした事例が存在します。5年を経過するギリギリに雇止めを行うことはもちろん、2、3年であっても、労働契約法の趣旨を潜脱するものとして、労働契約法19条1号、2号の該当性を検討され、場合によっては、雇止めを無効と判断される場合があるのです。
雇止めが無効とされる場合
具体的に、どのような場合に雇止めが無効とされるのでしょうか。
まず、労働契約法19条を見てみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
通達(平成24年8月10日付基発0810第2号。リンク)によれば、労働契約法19条1号、2号に該当する場合には、雇止めが無効であることを示しつつ、これまでの裁判例と同じような判断枠組みを用いて検討するとしています。
通達は、以下のような判断要素を例示列挙し、これらを総合考慮して、個々の事案ごとに判断するとしています。
- 当該雇用の臨時性・常用性
- 更新の回数
- 雇用の通算期間
- 契約期間管理の状況
- 雇用継続の期待をもたせる使用者の言動の有無
そして、通達は、労働契約法19条2号の「満了時に」とは、雇止めに関する裁判例における判断と同様、「満了時」における合理的期待の有無は、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されることを明らかにするために規定したものである、としています。
つまり、通達は、一度労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、有期労働契約の契約期間の満了前に、使用者が、更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに労働契約法19条2号に該当しなくなることにはならないと解しているのであり、通達は、2、3年後の雇止めでも労働契約法19条に抵触する可能性を否定していません。
また、労働者との合意(申込みと承諾)ではなく、使用者が一方的に契約の不更新を通告することは避けた方が良いでしょう。このような場合、多くの裁判例によれば、労働者の合理的な期待を失わせることは相当でないとして、雇止めが無効であると判断されています。
労働契約法18条からの視点
また、労働契約法18条2項も要注意です。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
18条2項は、要するに、契約期間中、働いていない空白期間が6か月以上ある場合は、当該5年間に算入されない、というものです。
ですので、休職期間などで勤務していない期間がある場合には、空白期間のチェックが必要です。空白期間が相当期間ある場合、労働した期間は2、3年と短いのに雇止めの問題が生じ得ることになります。
無期転換ルールに関する注意点
労働契約法18条により、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール、すなわち無期転換ルールが法定化されています。
企業としては、この無期転換申込権を事前に労働者に放棄させたい、と考えることはママあるのですが、このように事前に放棄させることは、公序良俗に反し無効であると解されています。
また、労働者による無期転換請求権の行使を受け入れる場合にも注意をするべき点があります。
無期転換を受け入れる場合、当該有期期間満了前の翌日から無期労働契約が成立します。したがって、それ以降、労働者を解雇する場合には、期間の定めのない労働者(端的には、正社員)と同様、労働契約法16条(解雇に関する定め)の適用があります。
他方、無期転換後の労働条件は、「現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件」であり、労働条件が同一であることを前提としています。正社員と同一の労働条件となるものではありません。
また、無期転換後の労働条件については、個別の合意、就業規則、労働協約など別途定めておき、正社員と違いを設けておくことは可能です。
もっとも、無期転換労働者について、新たな就業規則が作成され、その条件が従前の労働条件を不利に変更するものであるときには、労働契約法9条・10条の不利益変更禁止の規定が(類推)適用され、変更に至った経緯や、内容の相当性、労働者が被る不利益の程度などの事情を総合考慮して、その内容が「合理的」であると認められなければ、その部分の就業規則は無効となります。
小括
雇止めについてまとめると・・・
- 5年ギリギリで雇止めをすることは無期転換の制度を潜脱するものとして無効となる可能性が相当程度高い。
- 空白期間(休職などで労働していない状態等)が6か月以上ある場合、その期間は無期転換の5年間に通算しない。
- (そのこともあって)2年間や3年間労働した場合でも、場合によっては労働契約法19条によって、雇止めが無効とされる場合もある。
- いわゆる不更新条項(次回からは契約を更新しない旨の合意)については、労働者の真に自由な意思によりなされた場合には、有効なものとなるが、そうは評価されない場合、雇止めは無効となる。
- 無期転換を受け容れた場合、労働条件の変更には注意を要する。
ということになろうかと思います。
多少複雑なように見えますが、紛争になるケースも数多くみられるところですので、企業運営上欠かせないルールであると言えます。
次回は、労働組合対応についての一般論を解説したいと思います。
執筆: 弁護士 森村 直貴